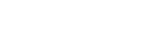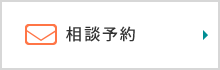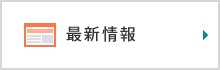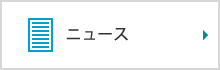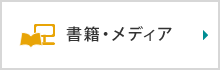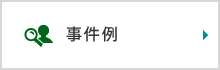【2024.10.22 石田和外最高裁長官は、本当に公害裁判における被害者救済を訓示したのか?】
1 石田和外長官の二面性
9月12日放映の「虎に翼」をもとに、公害裁判の原告救済判決と最高裁との関係について考えてみます。
「虎に翼」の桂場等一郎氏のモデルは、いうまでもなく、石田和外第五代最高裁長官です。
石田長官は、青法協の宮本康昭裁判官の再任を拒否するなど、裁判所内のリベラルな思想の裁判官たちに激しい迫害を加えた中心人物です。最高裁の労働基本権の保障に関する全逓中郵事件判決など1960年代の基本権を拡大する方向の判決を、73年に全農林警職法事件を主導して逆転させた保守回帰の時代の最高裁長官でした。そして、73年の長官退任後には日本会議のもととなった元号法制化国民会議の代表などもされていた方です。
他方で、このあとのドラマでも描かれましたが、73年の尊属殺人厳罰規定の大法廷違憲判決時の長官でもありました。
そして、当時多くの公害裁判が闘われていました。四日市の大気汚染、水俣病、イタイイタイ病など、多くの公害訴訟で原告側が勝訴する判決が出されました。四大公害裁判の判決で次々に被害者救済の判決が続けて出された背景には、当時の最高裁からの強い後ろ盾があったこともまぎれもなく歴史的事実です。
2 「虎の翼」の脚本には史実の裏付けがある
ドラマでは星航一裁判官(三淵乾太郎)が桂場に対して、「ご存知の通り、損害賠償裁判は、被害を受けた原告側が被告の過失を立証する責任があります。それゆえに公害裁判は、被告である企業側が原告の主張に科学的根拠がないと言い張り、長期化してしまう」と述べたのに対して、桂場長官(石田和外)が「裁判長は、推論により因果関係が認められれば、原告側の主張は成立していると判断する。企業側が不服であれば、過失がないことの立証をするよう求める」と述べます。
その後、星裁判官が「ないことを立証するのは、困難では」と返すと、桂場長官は、「公害被害で苦しんで助けられるべき人は、速やかに助ける。それが、司法の力であるべきだ」とのべます。そして、ナレーションでは、「この新たな法解釈の検討は、膠着していた公害裁判を一気に原告勝訴へ導く、大きなきっかけとなりました」と結ばれました。
これから説明するように、このようなやり取りは、歴史的な事実に沿うものであり、次のような歴史的経過をまとめたものです。
最高裁判所は、1970年代に、四大公害裁判において、最高裁長官、事務総局、民事局、下級審裁判所が連携し、研究と討議を尽くし、因果関係と過失の立証責任の転換を図るなど、新たな法概念を採用し、公害事件の被害者の早期救済に取り組みました。
今の最高裁には、このような歴史的経験を思い返し、東京電力・国の影響をうけることなく、福島原発事故の責任をめぐる裁判において、国と東京電力、とりわけ東京電力の元役員の責任を明らかにする、毅然とした司法判断を行うことを強く期待して、歴史的経過をまとめてみます。
3 マイノリティに焦点を当てたドラマ「虎に翼」と四大公害裁判における被害救済
「虎に翼」は、日本初の女性弁護士であり女性裁判官であった三淵嘉子さん(猪爪寅子さん)の生涯と、彼女が遭遇した司法の歴史上の重要な出来事を、憲法14条の法の下の平等の実現をキーワードとして描かれた、リーガル・エンターテインメントでした。そして、このドラマの第二の主役は、寅子さんと明治大学の女子部の仲間たちでした。弁護士である夫との関係に悩む主婦、家庭内暴力の被害者、韓国からの留学生、華族のお嬢様とその付き人という仲間たちの問題も詳しく描かれました。
そして、様々なマイノリティが、これまでずっと感じて来た「生き難さ」に形を与えて、言語化し、国民全体がきちんと考える課題に押し上げたといえます。
2024年7月3日、最高裁判所大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は、裁判官全員一致で、旧優生保護法に基づき不妊手術を強要された各地の被害者らが提起した国家賠償請求訴訟について、原告側勝訴の判決を言渡しました。優生保護法による強制不妊手術の強制について、法の制定当初からの違憲性を明らかにし、民法の定めていた除斥期間の壁を打ち破って救済した最高裁判決は、自民党総裁選挙=首相の交代と衆院解散という情勢の下であわただしく開かれた特別国会で、唯一超党派で起草され提案された救済法案の成立という画期的な成果につながりました。
「虎に翼」のドラマは、後半になって、司法の抱えている深刻な問題にどんどん鋭く切り込むようになりました。原爆裁判、公害裁判、ブルーパージ(青法協裁判官に対する差別と排除)、少年法改正、尊属殺人など、司法の世界を揺るがした重要な出来事が、次々に取り上げられました。
4 1970年、1971年の裁判官会同と矢口元長官の証言
(1)裁判官会同であらたな法理論の必要性を説いた石田長官
1970年当時、多くの公害裁判が闘われていました。四日市の大気汚染、水俣病、イタイイタイ病など、多くの公害訴訟で原告側が勝訴する判決が出されました。
以下の文章は、京都大学が発行する『経済論叢』の第157巻第5・6号(1996年5・6月号)に掲載された松野裕教授による「公害健康被害補償制度成立過程の政治経済分析」と題する論文からの要約・引用です。
1970年3月12・13日、最高裁は公害訴訟の処理について民事事件担当裁判官会同を初めて開き、全国の担当裁判官が参加しました。この席で石田和外最高裁長官は「伝統的な法解釈、運用だけでは十分な処理は期待できない。今や新しい解釈方法が必要である」と述べたとされます(山本祐司「最高裁判所物語」講談社α文庫 46頁)。
そして、参加裁判官の間では因果関係の挙証責任の転換や無過失責任を採用すべきだという意見が強かったといいます(朝日新聞1970年3月14日)。
また、最高裁自身の考え方は同月20日の衆議院法務委員会で明らかにされました。矢口洪一最高裁民事局長はまず因果関係も過失も事実上被告側に立証責任を持たせる、というのが参加者の意見であったことを認め、それは現行法でできるのか、との問いに対し、実際問題としては「いわゆる事実認定の問題で相当数片がつくのではないかと考えており」、その場合に「一応の推定ということで立証ありとし」「いわゆる疫学的方法」を「これに導入することによりまして、なお事実の認定が容易になるということで、ある程度できるのではないかと思っております。」と述べています。矢口局長は、最高裁の見解として、因果関係、過失認定の挙証責任の転換さらには疫学的手法の採用は現行法でできるという全くの新判断を示したのです。また、現行法の解釈でやれるという説明は、この転換が遡及性をもち過去の汚染による損害賠償についても適用されることを意味しています。
矢口はその著書の中でこの会同に触れ「多くの成果を生んだ。」と評価し、石田も後に「(四大公害裁判では)裁判所としては百%の任務完遂と思っています」と述べています。これらの発言は最高裁が公害裁判の結果に影響力を与えたことを認めたものといえるでしょう。また、朝日新聞は会同から半年後、最高裁が上記の考え方をまとめたものを参考として担当裁判官らに配布したことを示唆しています(松野論文・57頁~58頁)。
(2)矢口洪一氏の証言
矢口洪一氏は、当時の最高裁民事局長であり、後に最高裁長官にまでなった裁判官です。また、矢口氏は石田長官とともにブルーパージを指揮した方ですが、自ら長官となったのちには、青法協裁判官に対する差別的取り扱いを止めるべく努力したことでも知られています。
矢口氏は、1993年に書かれた『最高裁判所とともに』と題した著書において、次のように述べ、四大公害裁判における原告勝訴判決は、最高裁主導で会同を開いて、裁判官の研鑽を図った成果であると述べています。
「最高裁民事局長時代の昭和四五年三月、全国の高、地裁の民事担当裁判官五七人を集め、公害訴訟の処処理に関する会同を聞いた。後になると、最高裁事務総局が下級審の裁判官を集めて訴訟の検討会を聞くとすぐ「個別の訴訟への干渉」などと批判されかねなかったが、これは公害問題に対する世論の関心もあって多くの成果を生んだ。
一つは「疫学的因果関係」という考え方の導入である。従来、公害訴訟で不法行為を立証するには、被害者側に症状と原因物質との聞の因果関係を逐一証明する責任が求められた。しかし実際には科学的知識や資力の面で被害者側に困難な面が多かった。
そこで、元来伝染病などの流行の系統や原因解明に使われてきた疫学の統計的手法を採用し、これが認められれば法的にも因果関係は十分、と考えてはどうかという意見が出された。逆に企業側は「過失なし」を自ら立証することとなるわけである。
東京スモン訴訟の判決では「診断された患者のほとんどが発症前にキノホルムという薬剤を服用していた」「キノホルムが多く使われた地域でスモンの発症が多い」「医学理論上からも両者の関係は矛盾しない」などから、因果関係を認めている。
この疫学的因果関係の立証で被害者側の立証責任は事実上大幅に軽減された。もちろん、このような対応にあたって、被害者の救済という目的がまずあったわけではない。ただ、ほうっておくと公害裁判は何年たっても結論が出ない可能性があり、みんなの力で新しい局面を切り開こうという思いが裁判の一線に広がっていたことは確かだろう。
学者は学会の場で学説を検討にさらし、共同研究という場もある。裁判官だけが訴訟技術や社会の動きに関して意見を交換する場を閉ざされるというのはおかしなことで、極論すれば他人の書いた本も読めない、ということになる。新しい社会事象が起きて訴訟の規模が大きくなれば、裁判官個人が新しい局面を切り開く能力には限界も出てくる。
会同ではどういうふうに訴訟技術を使えば事態を打開できるか、意見交換したわけで、結論は担当裁判官が自由に判断することに変わりはない。」(矢口洪一「最高裁判所とともに」65頁~67頁)
「四大公害訴訟では、四日市ぜんそく訴訟の判決が引き金となって公害健康被害補償法ができるなど、救済制度が確立した。司法がそれになにがしかの貢献ができた、という自負はある。」(矢口洪一「最高裁判所とともに」65頁~67頁)
まさに、矢口元長官は、四大公害裁判における原告の早期救済は、最高裁以下の裁判所が取り組んだ成果であると自画自賛しているといえます。
(3)矢口洪一氏の国会における答弁
それでは、この問題についての矢口民事局長に対する1970年3月20日衆議院法務委員会における答弁を見てみることとします。
「○岡沢委員 最初に最高裁のほうに、この三月十二日、十三日、俗にいわれる公害担当裁判官会同というのがなされたことを新聞等で承知しているわけでございますが、この会同のときに出た意見の中で、特に今後の裁判上あるいは法制上参考になると思われるようなものを、簡単でけっこうですが御報告を願います。
○矢口最高裁判所長官代理者 ただいまお尋ねの会同は、今月の十二、十三日の二日にわたって行なったわけでございます。問題になりました大きな点は二点ございます。
まず第一点は、公害の原因とその公害によって生じたもろもろの結果があるわけでございます。その結果の間のいわゆる因果関係の問題をどのように訴訟手続上認定していくかという問題であります。
それと関連いたしまして、必然的にその因果関係が認められるとしても、そういった原因から——いわゆるその原因を起こすものは一般的には企業者ということに相なるわけだと存じますが、その企業者のどのような過失によってその原因があり、その原因によってどのような結果が生じたか、いわゆる過失の問題の認定でございます。
因果関係の認定の問題と、過失の認定の問題をどのように訴訟手続の経緯においてとらえていくか。これまでの不法行為論からまいりますと、被害を受けたとして請求をいたします原告の側におきまして、厳格な過失の主張をし、厳格な過失の立証をし、かつ因果関係について厳格な主張、立証を行なわなければならないということでございますが、このようになってまいりますと、実際問題として、非常に多数ございます被害者は一般の市民でございますが、専門的な知識も乏しゅうございますし、資力もまた必ずしも十分とはいえないのが実情でございます。したがいまして、いままでの市民法的な原理に立ちます民事訴訟法のやり方をそのまま適用してまいりますと、どうしても原告と被告の間に実質上の平等ということが期し得ない。その期し得ない間隙をどのような訴訟技術をもって埋めていくかということが会同員一同の最大の関心事であったわけでございます。
その次に問題になりましたのが、現実に日々生起しております被害を目の前にいたしまして、とりあえずその原因の発生をとめていくという観点からの差しとめ請求権というものをどのような形で認めていったらいいだろうかということが第二点であったわけでございます。
このまず最初の点につきましては、訴訟の技術の問題になるかとは存じますが、事実の推定という考え方あるいは蓋然性の理論、可能性の理論と申しますか、そういったものを広範囲に取り上げていくことによりまして、一般的にこういうことからこういうふうになったと思われるような事実関係が大体わかるならば、逆におれのほうはその結果に対して原因を与えていないんだということを加害者側に立証させること。加害者側がそのような立証ができないならば、むしろ最初の蓋然性そのものによって十分の立証がある、このように考えていったらどうか。過失の点も同様でございます。そういうふうな考え方を取り入れることによって、当事者双方の実質上の対等を期していきたいということでございます。
それから差しとめの問題は、これは現在有害な煙を出しておる煙突がかりにあるといたします。その煙突から煙を出すなということは、これまでの訴訟理論によっても当然可能であるように考えております。しかし、さらにもとへさかのぼりまして、その煙突をこわしてしまえ、あるいはその煙突から煙を出しておるもとの機械を撤去してしまえ、あるいはさらに別の観点から、煙突から煙を出してもいいけれども、有害な煙を出さないような設備をそこにつけていってはどうかというような、いわゆる差しとめといいますと一般的に消極的なものでございますけれども、これを一歩進めまして、積極的に、ある行為をしろというふうな差しとめができるかどうかということが問題になりました。この点につきましては、ある程度現行法でもできるのではないだろうかというようなことと、それから終局的には、これを満足させるためには新しい立法が必要ではないだろうかという考え方と、双方とも相譲らない二つの意見が出てきたわけでございます。そういう点につきましては、今後もう少し事件を重ねてまいりませんと、いずれの問題も明確な答えを出し得ないというのが会同員一般の考え方でございまして、もしそういうふうな一つの方向が出てくるならば、それはそれで立法措置なり何なりをまたあらためて検討することにしたらどうかというふうなことで会同を終わった次第でございます。
○岡沢委員 いまの第一点の問題は、私の解釈が誤りでなければ、挙証責任の転換の問題だと思うのでございますけれども、これはそのときの意見でもけっこうですし、最高裁の御見解でもけっこうなんですが、現行法を変えなくても解釈でまかなえるという御趣旨かどうかということが一点。
それから、第二点の差しとめ請求の問題、これはいまのお答えでも、現行法でやっていけるという意見と、やはり新しい法が必要だという意見があったということはよくわかりますが、またかなり大きな法律的な課題でもございますから、慎重にお取り計らいいただくということもわかりますけれども、一方で公害は現実の問題として全国で毎日起こっており、被害者が健康あるいは生命を害されているわけでございますから、やはりかなり喫緊な解決を求められている問題だと思いますし、また現に裁判所の判断も、もう訴訟にもなっているケースも少なくございませんし、現実にもう回答を出さなければいけない問題だと思うのでございますが、その辺について重ねてお尋ねいたします。
○矢口最高裁判所長官代理者 最初の立証責任、主張責任の問題は、実際問題といたしましては、事実の認定を、どのような限度でそういう事実ありと認定するかといういわゆる事実認定の問題で相当数片がつくのではないかと考えております。その場合に、先ほど申し上げましたように、一応の推定ということで立証ありとし、あるいはそれに加えますのに、このごろよく利用されておりますいわゆる疫学的方法と申しますか、大量観察的な方法、そういったものをこれに導入することによりまして、なお事実の認定が容易になるということで、ある程度できるのではないかと思っております。差しとめ請求は先ほど申し上げたとおりでございます。
ところで、理屈、解釈の態度等はそのようでございますけれども、実際の訴訟は現に係属しておりまして、一刻も早く正当な権利を有する被害者の救済は行なわなければならない現状でございます。で、専門的知識あるいはそれに対する準備等は十分必要でございますが、現段階におきましては、私どもはできるだけ専門家の方を、個々の事件について、あるいは鑑定人なりあるいは証人なりという形でお願いすることによってそのギャップを埋めていきたい、そのように考えているわけであります。」
このように、最高裁の現職の民事局長が、国会の法務委員会の場で、
・当事者間の実質的な平等を図るため、因果関係と過失の認定について立証責任を転換する。
・事実の推定、蓋然性の理論の法理を採用する。
・一応の推定ありということで立証ありとする、疫学的手法、大量観察法を用いる。
・これらの考えは立法の改正を待たずに適用できる。
という踏み込んだ見解を答弁していたことがわかります。そして、このような状況の下で、四大公害裁判の原告勝訴判決は出され、速やかに確定されていったのです。
(4)1971年11月の公害事件担当裁判官による第二次裁判官会同
松野論文によれば、その後の展開について次のように説明されています。
「イタイイタイ病・新潟水俣病裁判の判決がでた後の1971年に最高裁は2回目の会同を開いた。この席で石田長官は、全国の「裁判官の創意と努力により、既にいくつかの新しい法理と慣行が打ちたてられている」と述べ、事実上の因果関係の推定や無過失責任を採用した判決を支持した。またこの会同では、コンビナートの大気汚染のような複合公害について共同不法行為が成立するかが一つの論点であったが、矢口が前記著書で、公害訴訟の結果の救済制度の確立には司法も貢献したという「自負」がある、と述べていることなどから、ここで最高裁は「成立する」という見解を示したものと考えられる。これは前年のルール転換をさらに徹底するものである。」(松野論文58頁)
複合的不法行為についての共同不法行為についてまで、裁判所は踏み込んでいたことがわかります。
5 四大公害裁判における因果関係と過失の立証責任転換を理論的に根拠づけたのは、現職裁判官による司法研究であった
(1)東孝行『公害訴訟の理論と実務』
矢口洪一民事局長が、国会でこのように自信をもって答弁できたのは、なぜなのでしょうか。どうして、判決例がない中で、ここまで理論的に踏み込む答弁をすることができたのでしょうか。何か、石田長官と矢口民事局長の自信を支えた理論的根拠があるはずだと考えて、探索を試みてみました。
その謎を解くカギは、一冊の現職裁判官が行った1969年にまとめた『司法研究』とこの司法研究にその後の研究成果をまとめて1971年に出版した一冊の本にあることがわかりました。
この本は、出版当時大阪地裁判事補であった東孝行氏による『公害訴訟の理論と実務』という本です。東弁図書館の開架書棚にありました。
この本は、はしがきの冒頭で「本書は、理論と実務との接点に立った公害に関する民事訴訟の実体法的、手続法的研究の書である。」とされています。
「その考察にあたって貫かれている基本的な考察の姿勢は、公害司法(公害裁判)の「安定した進歩」ということである。R・バウンドは司法は安定していなければならないが、しかもまた静止しているわけにはゆかぬ、と論破した(細野武男訳・社会学的法学(一九五〇年訳)七頁)。安定は法的安定、法の継続性を意味し、進歩の動因は、公害紛争の公平な解決、ひいては、公害に対する人間と環境の保護の理念を追求することである。本書において、随所に、法的安定性、法の継続の見地からの検討を惜しまず、他面、その上に立って、法と法解釈論の修正に努力しているのは、その基本目線にそったものである。」と説かれています。
東判事補は、1969年に、在外研究の成果を含む『司法研究』を既に公表されていました。「公害による賠償請求の訴訟」司法研究報告書第二二輯第一号〈昭四四〉」がそれです。本書は、公害裁判を審理する地裁との討議を通じて深められたものであることが次のような記述から裏付けられます。
「本書の基本になっている司法研究に際しては、司法研修所の当時の所長鈴木忠一先生、教官藤井正雄先生をはじめ資料課の方々の御指導を受けたほか、当時公害事件が係属していた新潟地方裁判所、富山地方裁判所、津地方裁判所四日市支部、ならびに弁護士正力喜之助氏その他諸賢から貴重な資料の提供をいただき、御意見をきかせていただいた。そして、司法研修所は、この度の公刊を快く承諾され、また、前記論文の付加収録を快諾していただいた。」
1971年8月 著者
〔追記〕本書の脱稿ののち、いわゆる新潟水俣病判決(1971年9月29日判決)が言渡された。本書をできるだけアップツウデートなものとするために、この判決の法解釈学上の位置づけを試み、第七章、第五節として挿入することにした。簡単ではあるが、読者の皆様の参考となれば幸いである。」(同書4頁~5頁)
このような、法的な安定性と権利の救済を両立させる考え方は、まさに、裁判官にとって、最も大切な基本的なスタンスではないでしょうか。
(2)東氏による因果関係と過失についての立証責任の転換
「現在係属中のいわゆる公害裁判のうち、すでに第一審判決があったイタイイタイ病事件、新潟水俣病事件、水俣病事件、四日市公害事件のいずれをとってみても、因果関係の立証が様々な形で争点となっている。このことは、公害紛争においては因果関係の立証がどんなに困難なものであるかを実証するものである。果たして、刑法の分野では、前述のように、いわゆる公害犯罪処罰法五条は、因果関係の一部分につき推定規定をおき、加害者側にその事実の不存在につき立証責任を負わせた。ただ、これは因果関係の事実のすべてについてでなく複数の発生源がある場合、いずれが加害者であるかについての推定である。ここでは、この規定につき詳論するいとまがないので、この刑罰規定も公害における因果関係の立証の困難さをうかがわせ、かっ、これに対する法制度としての姿勢を示したものとして理解することができる、ということだけを指摘しておこう。」(同書174頁)
「ところで、われわれは、単に因果関係の立証が困難である、ということから、直ちにこれを緩和すべきだ、という結論を導きだせるものではない。ここに、もう一つの要素がある。それはつぎのような事情である。公害現象においては、通常、加害者は社会的、経済的にも専門知識の上でも、優位な立場にあり、被害者は劣位の立場にあることが多い。かつて「裁判所法の一部を改正する法律」(昭和四五法六七)の制定に際し、参議院法務委員会が、附帯決議の一つとして「民事事件に沿いては、公害事件の挙証責任について、被害者側の負担を軽減するようにすべきである。」と決議したのも、以上の点に対する配慮からであることは明らかである。このような公害における因果関係の立証の困難さと、加害者と被害者との社会的、経済的、専門知識上の地位の格差の存在との両方の事情が存するところから、公害紛争における因果関係の立証の緩和が何らかの形で考えられなければならないことになる。」(同書・175頁)
「このように、従来の裁判例において「一応十分な証明」の理論を因果関係の立証について採用しているのであれば、公害紛争における因果関係の立証について、この理論を採用することは、法状態の継続、法的安定性の見地からも何ら支障がないことである。そのうえ、前述のように、この理論の最大限の運用が公害紛争における当事者の公平という法の根本理念にそうならば、もはや、形式的にも実質的にも、この「一応十分な証明」の理論を公害紛争の因果関係の立証に適用することができることになる。」(同書・201頁)
ここで説かれている法理は、まさに矢口長官が国会で説明したものであり、四大公害裁判の原告を救済した判決に共通するものでした。これらの判決は、そのほとんどが一審で企業側が控訴することなく確定しました。最高裁の判断がどのようなものとなるか明らかだったからです。そのために、この理論を指示した最高裁判決が存在しません。そして、そのことが、今日、東京電力などが原告あるいは検察官の側に全面的な因果関係の立証責任を負うとの主張を展開することを許すこととなるという、皮肉な結果を産み出しているのです。
6 変わり果てた最高裁、その再生は本件において、東京電力役員の責任を明らかにすることなくしてあり得ない
(1)下級審が積み重ねてきたものをなぎ倒した最高裁多数意見
1970年代の司法と2010-20年代の司法を比較して、大きく様変わりしてしまったのが、最高裁の役割であることがわかります。
2022年6月17判決前には、圧倒的に多数の下級審裁判所において、福島原発事故の責任が、原子力の安全性を確認していた国にもあることを認める判決を重ねてきました。
2022年6月17日判決は、国の福島原発事故責任を否定しました。下級審の裁判官が積み上げた努力を文字通り、なぎ倒したのです。
この判断は果たして、最高裁の一致した見解だったのでしょうか。判決には三浦裁判官による、詳細な反対意見が付されていました。
意見の体裁からして、この三浦意見こそが、最高裁の調査官室が準備した法廷意見の原案だったのではないかと私たちは想像しています。
意見の体裁とその内容だけが根拠ではありません。
(2)ついに民事訴訟法専門家からも批判されるに至った最高裁判決
2022年6月17日判決は、最高裁民事裁判例集=民集に掲載されました。しかし、判例タイムスと判例時報に短い解説は掲載されましたが、法曹時報への判例解説は掲載されていません。その理論的な根拠は明確となっていないのです。
この判決に対する、環境法学、原子力法制の専門家の批判は極めて厳しいものであることは当然のこととして、(下山憲治・判評 777号8頁(判時2570号126頁)、山田健吾・環境法研究 48号93頁)、民事訴訟法研究者による、最高裁判決が民事訴訟法に違反しているという指摘が重要です(長島光一・判時2543・2544号129頁)。この最高裁判決が、前提となる事実関係について高裁までの議論を基本としていないのです。
最高裁は法律審であり、事実認定を問題とするときは経験則違反として、破棄して是正を命ずることはできます。ところが、6.17判決は民訴法321条に反する違法な事実認定を行っているので、長島氏は、先例としての拘束性はないと言い切っています。
また、判例時報の2546号に掲載された、6.17判決の解説も注目されます。判決内容の客観的な説明に終始し、菅野、草野補足意見と、三浦反対意見が、論評抜きで紹介されています。さらに、「本件において結果回避可能性が認められないことの法的な位置づけ、すなわち、これにより規制権限不行使の違法性が否定されるのか、因果関係が否定されるのかという点については、本判決(多数意見)はその立場を明らかにしていない」と指摘されています。この判例時報の判例解説は、判決を言い渡した裁判官、最高裁判決の場合であれば、担当調査官が書くことが、長い慣行となっています。そうしてみると、この解説の記載は、多数意見は、調査官が書いたものではないことを問わず語りに明らかにしているようにも見えます。
(3)かつてない司法への不信の高まりに最高裁は正面から向き合い、自らの誤りを正すべき時だ
最高裁を舞台に言い渡された6.17判決は、その結論だけでなく、審理の在り方、判断をした裁判官の東京電力からの独立性に疑問が提起され、司法は本当に東京電力や国から独立しているのかという、深刻な疑念を、広範な市民に引き起こしています。
福島原発事故の責任を明らかにすることは、原発のあらたな過酷事故の再発を食い止めるための第一歩です。
1970年には、保守的思想の巨頭であった石田和外最高裁長官が持ちえた、「公害の被害者は救済しなければならない、このような被害を再発させてはならない、そのために司法は一歩前に出なければならないはずだ」という当然の信念を、いま現在の最高裁判事も、共有できるはずだと信じます。
最高裁が、東電刑事裁判について高裁の言渡した無罪判決についてその破棄を命じ、事件の審理を原審に差し戻す判決こそが、危機に立つ司法を救う道です。
そして、東京地裁商事部が東電役員に対して13兆円余の支払いを命じた2022年7月13日判決の東電株主代表訴訟の控訴審において、東電役員側の控訴を棄却し、東電役員の事故発生についての責任を明確にすることもまた、司法を担う多くの裁判官の覚醒につながり、電力事業者に厳しい自己規律を求めるものになると信じます。
<参考資料>
1 松野裕「公害健康被害補償制度成立過程の政治経済分析」
2 矢口洪一『最高裁判所とともに』
3 1970年3月20日第63回衆議院法務委員会
4 東孝行『公害訴訟の理論と実務』
5 山本祐司『最高裁判所物語』講談社α文庫