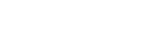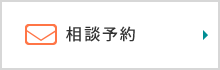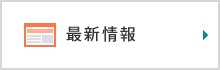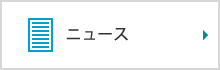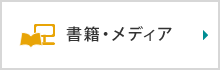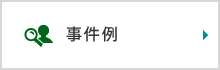2020年9月 弁護士鬼束忠則 (2020年10月加筆修正)
今年2020年の4月1日から改正された民法が施行されました。今回の改正は民法の広範な領域に及ぶものですが、購入したり建築したりした住宅に欠陥があった場合の売主や建築業者の担保責任に関する規定についても大きな改正が行われました。
今年の2020年3月31日までに住宅の購入契約をしたり、建築請負契約をした場合には、改正前の民法(以下「旧民法」といいます)が適用されますが、2020年4月1日以降にこれらの契約をした場合は、改正後の民法(以下「新民法」といいます)が適用されることになりますので、それぞれ注意が必要です。
それでは以下に、旧民法が適用される場合と旧民法が適用される場合の欠陥建築を是正するための法的手段の違いについていくつかの場面に分けてみていきます。
1 売買の場合
(1)旧民法の適用がある場合(つまり2020年3月31日までに売買契約を締結した建物の場合)
【ポイント】
●旧民法では、購入した建物に欠陥(「瑕疵」といいます)があることを知ったときから1年以内に、損害賠償を請求する旨を売主に通知すれば建物の引き渡しを受けた時から10年間は損害賠償を請求できます。この通知は、内容証明郵便などで行えば足り、裁判などの法的手段を取るまでの必要はありません。
●これらの期間については売買契約書に「建物の引き渡しを受けた時から2年のうちに通知しなければ、損害賠償請求はできない」といった条項があれば、それに従うことになります。もちろんこの場合も2年間のうちに通知をすれば、引き渡しの日から10年間は損害賠償請求をすることができます。
●もっとも、2年間の期間の制限をした上記のような契約条項があっても、「建物の構造耐力上主要な部分」又は「雨水の侵入を防止する部分」に関する瑕疵については、建物の引き渡しを受けた時から10年間は、上記の通知をしていなくても、必ず損害賠償請求と瑕疵の修補請求をすることができます。これは、通称「品確法」と呼ばれる法律によります。これらの瑕疵の場合は、契約書でこの期間を短縮することはできません。
【以下旧民法での売買契約の責任追及について詳しく見てみましょう】
ア 損害賠償請求
住宅(マンションも同じ)の買主は、住宅に欠陥があること(これを旧民法では「瑕疵(かし)」と呼んでいました。)、さらにその瑕疵について売主に対し責任を確実に追及できるということを知った時から1年以内に、売主に対し、損害賠償をする旨を明確に告げれば、引き渡しの日から10年間損害賠償請求をすることができます。1年以内に裁判までを起こす必要はありません(旧民法570条、566条1項後段、同3項)。ただ、このような通告は口頭ではなく内容証明郵便などを用いて、文書で行った方がいいでしょう。
この規定からお分かりのように、買主は瑕疵の存在を知った時から1年間のうちにこの通告をすればいいので、例えば住宅を購入した7年後に初めて瑕疵の存在を知ったとしても、その後1年内に通告をすれば、その損害賠償請求権は保存できます。
しかし、次の2点に注意が必要です。
まず第1点。住宅の売買契約後に、実際に住宅の引き渡しを受けた時から10年間が経過すればこの損害賠償請求権は時効により消滅する状態になりますから(旧民法167条)、10年経過後の請求は、売主に「損害賠償請求権は時効によって消滅した」という主張を受けることになります。また、たとえ、瑕疵の存在を買主が知らなくても10年間が経過すれば時効にかかってしまいます。
次に第2点目。上記の「知ってから1年以内の通告」という民法の規定は、売買契約書の規定によって、「建物の引き渡しを受けた時から2年間(あるいは3年間)が経過したときは(瑕疵に気づかなくても)損害賠償請求はできない」という内容に変更されている場合がほとんどです(お持ちの契約書の「瑕疵担保責任について」という条項を見てください。)このように売主が瑕疵担保責任を負う期間を制限することは有効であるとされています(私は、実際にこのような制限があることについて売主が買主に説明することは稀ですので、一律に有効とすることはおかしいと考えていますが。)。
したがってこのような契約条項があると、「知ってから1年以内」に損害賠償請求をするとの通告をすれば権利が保全できることにはならず、例えば引き渡しを受けて2年が経過すればそもそも損害賠償請求権がなくなってしまうことになります。そのため、住宅の引き渡しを受けたのちできるだけ早く瑕疵があるかどうかをチェックをする必要があります。なお、中古住宅の売買の場合はさらにこの期間を、引渡を受けてから3か月とか6か月という短い期間にした契約条項もありますので、注意してください。
イ 瑕疵の修補請求と損害賠償請求
上記アで述べたのは新築住宅か中古住宅かを問わないものです。
しかし、新築住宅の場合は、特別の規定があります。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」といいます。)により、新築住宅の売買契約(請負契約の場合も同じ)の場合は、「引き渡しを受けた時から10年間」は瑕疵担保責任を追及できるとして旧民法の規定を修正しています。上記のように、2年の経過によってあらゆる瑕疵について瑕疵担保責任を負わなくするというのはあまりに買主に不利益だからです。
さて、まずここでいう「新築」というのは、建築してから1年以内の建物でまだ人が住んだことがない建物をいいます。ですから、完成から1年を超えた建物、1年以内でもすでに人が住んだ建物は「新築」ではなくなり、「中古」とされますから、この法律の適用はありません。
次に、この法律で可能な瑕疵担保責任の追及の方法は、瑕疵の修補請求、またはこれに代わる、あるいは修補請求とともにする損害賠償請求をいいます。旧民法の規定では、損害賠償請求しか認められていませんが、それに加え修補請求をすることができます。
ただし、これらの請求ができるのは、新築建物にあるすべての瑕疵ではなく、「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」に制限されています。「構造耐力上主要な部分」というのは、基礎、土台、柱、壁、梁などの建物にかかる荷重や、地震力などによる震動や衝撃を支える部分をいい、「雨水の浸入を防止する部分」というのは文字どおり、雨などが建物内に浸入するのを防止する屋根や外壁など、これらに設けられた開口部のサッシや戸などの建具など、さらには建物内に造られた雨水の排水管をいいます。これらの部分に瑕疵があれば、10年間の瑕疵担保責任を追及できます。
この品確法の規定は「強行規定」といわれるもので、売主と買主間でこの期間を短縮したり、上記の瑕疵の内容を制限したりする契約や同意は無効となります。
(2)新民法の適用がある場合(2020年4月1日以降に売買契約を締結した場合)
新民法では、これまで述べてきました旧民法の規定を次のように改正しました。
① 「瑕疵」という言葉を使わず、「目的物(ここでは住宅)が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」という表現になっています。
これは「契約不適合」と呼ばれます(新民法562条1項)。
ただ、この「契約不適合」の内容は、旧民法の「瑕疵」の内容と同様に考えていいと思います。つまり「契約不適合」というのは、❶売買契約に定めた内容と異なる場合❷法令に違反する場合❸通常の設計・施工水準に達していない場合が該当するということになります。
② このような「契約不適合」があった場合、買主は、売主に対し、目的物(ここでは建物)の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しを請求をすることができるとしました。これを「買主の追完請求権」と呼んでいます。
③ ただ、このような買主による追完請求に対し、売主は「買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」としています(同条但書)。
④ 買主が相当の期間を定めて上記の追完を求めても、売主がその期間内に追完をしないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができるとしました(新民法563条1項)。ただし、売主が追完を拒絶する意思を明確に表示したときなど一定の場合には、追完請求を先行しなくても直ちに代金減額請求できるとしました(同条2項)。
このように代金減額請求を行うには、追完請求(例えば修補請求)をまず行うことを原則とすることについては批判もあります(とくに後述の請負契約の場合)。直ちに代金減額請求を行うことができる場合をできるだけ広く認めるべきでしょう。
⑤ さらに、上記の追完請求や代金減額請求をする場合、あるいはそのような請求をしなくても、新民法415条の規定(債務不履行)に基づいて損害賠償請求や契約の解除(新民法541条、542条)もできるとしています。
ただし、旧民法の場合の瑕疵担保責任は無過失責任とされていましたので、修補請求に代えてする損害賠償請求の場合も売主の過失は問題とされていませんでした。ところが新民法では過失を前提とする損害賠償請求一般と同じ取り扱いをするということになると、売主の過失の存否が問題となることになり、場合によっては旧民法では認められた損害賠償が否定されるという事態になるのではないかと危惧されます。
⑥ 上記のような契約不適合の場合の買主の追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権および契約の解除は、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないとすることはできないとしています(新民法566条本文)。ただし、売主が引き渡しの時にその不適合を知っていたか、又は重大な過失により知らなかったときは、この期間制限は適用されないとしています(同条但書)。
つまり、通常の権利と同じように「権利を行使することができることを知った時から5年間」、又は「権利を行使することができる時から10年間」で時効によって消滅することになります(新民法166条1項1号及び2号)。
この規定の本文は、すでに述べました旧民法の期間制限と基本的に同じものです。したがって、この規定については売買契約において契約書に旧民法の時と同じように、例えば「追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除は、建物の引き渡しの時から2年が経過したときはすることができない」という条項を売主が入れ、そのために旧民法の時と同じ不当な結果をもたらすことになる危険性があります。
仮にこのような条項が契約書に入れられていても、少なくとも上記新民法566条但書のように「売主が引き渡しの時にその不適合を知っていたか、又は重大な過失により知らなかったときは、この期間制限は適用されないと」し、まったく期間制限がない状態、つまり、通常の権利と同じように「権利を行使することができることを知った時から5年間」、又は「権利を行使することができる時から10年間」で時効によって消滅する(新民法166条1項1号及び2号)と解すべきです。
⑦ 品確法との関係
新民法の上記のような改正に伴い、品確法の規定も、従来の修補請求権と損害賠償請求権だけでなく、追完請求権(修補請求もそのひとつ)、代金減額請求、損害賠償請求、解除権の行使を認める内容に改正されました(改正品確法95条1項、3項)。
なお、品確法が適用される場面、すなわち新築であること、瑕疵(契約不適合)が「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」に制限されていること、強行規定であることに変更はありません(同条1項、2項)。
さらに、品確法に基づくこれらの請求権は、品確法の特別法的性格から、通常の権利と同じように「権利を行使することができることを知った時から5年間」で消滅時効にかかる(166条1項1号)と解するのは誤りで、単に「権利を行使することができる時から10年間」で時効によって消滅する(166条1項2号)と解することになるでしょう。すなわち、新築住宅の引き渡しを受けてから2年後に「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」に瑕疵を発見しても、5年以内に裁判を起こさなければならないのではなく、発見してから8年以内に裁判を起こせばよいということになります。
2 請負契約の場合
(1)旧民法の適用がある場合(つまり2020年3月31日までに請負契約を締結した建物の場合)
ア 瑕疵の修補請求と損害賠償請求(瑕疵担保責任の内容)
旧民法では、注文者は仕事の目的物(本件では建物)に瑕疵があるときは、請負人に対し、瑕疵の修補請求と、瑕疵の修補に代えて又は瑕疵の修補ともに損害賠償請求をすることができます(旧民法634条1項、2項)。売買契約場合と異なり、基本的にすべての場合に瑕疵修補請求権を認めています。
イ 解除について
旧民法では、建物(その他土地の工作物も含みます)に瑕疵があり、そのために請負契約をした目的を達することができないときでも、契約を解除することはできないとされています(旧民法635条但書)。
この規定は、わかりにくいのですが、まず、この規定が適用されるのは、建物が一応完成した後の場面です。建物が一応完成した時以降は契約の解除はできないということになります。
しかしまだ建物が完成していない時(未完成の時)は次にように考えられています。建物が未完成の時に瑕疵の存在が明らかになり、その瑕疵の内容や規模からして、そのような施工者には補修やその後の施工をゆだねるだけの信頼を寄せることができないと認められる場合や、施工者の責任で建物完成が遅れ、かつ完成までにはかなりの期間を要するために契約の目的が達成できないという場合などは、契約の解除が認められることもあります。
次に、では完成してしまうと、施主は、どんなにひどい瑕疵があってもその建物の存在を前提として受け入れ、あとは補修請求と損害賠償請求だけしかできないのかという問題があります。これについては、最高裁判例(2002年【平成14年】9月14日)が次のように述べています。「建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、当該建物を収去しても社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、建て替えに要する費用を請負人に負担させても請負人にとって過酷であるとは解されないから、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額を請求することができる」としました。要するに、施主は、完成した建物に重大な瑕疵、たとえば構造上の重大な瑕疵があるため危険な建物であり、それを建て替えなければならないときは、その建物を解体する費用と再築費用の損害賠償請求を請負人に対して請求することができるとして、実質的に請負契約を解除した場合と同じ効果を求めることができるとしました。
ウ 瑕疵担保責任の存続期間
旧民法は、建物その他土地の工作物又は地盤の瑕疵について、その引渡の時から、木造の場合は5年間、その他鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの堅固な建物については10年間、注文者は上記の瑕疵修補請求および損賠賠償請求をすることができるとしていました(旧民法638条1項)。ただ、この期間については、当事者の合意によって短縮できると解釈されており、一般的には請負契約書に1年ないし2年に短縮するとの条項が置かれています。
このような期間を制限する条項は、請負契約において、請負人から注文者に対し、ほとんど説明もなく、したがってほとんどの注文者がこの条項の存在にさえ気づかないで契約を結んでいるという現状があり、瑕疵が発覚したあとに初めてこの条項の存在に気づき、しかし、その時には瑕疵担保責任を追及することができる期間がすでに経過してしまっているという不当な結果をもたらしています。
このような不当な結論を少しでも是正するために、建物の引き渡しの時点で請負人が瑕疵の存在を知っていたか、あるいは重大な過失によりそれを知らなかった場合は、上記のような瑕疵担保責任を追及できる期間を短縮する合意は無効であると解釈した裁判例もあります。なお新民法では、請負人が、建物の引き渡しの時に、建物に契約不適合の状態(これは「瑕疵」の内容と同様と考えてよいです。)を知っていたか、又は重大な過失により知らなかったときは、この期間制限は適用されないとしています(新民法637条2項)。旧民法の適用がある請負契約の場合についても、新民法のこの規定の趣旨を積極的に援用して、注文者の被害を救済していく必要があります。
エ 瑕疵担保責任の存続期間と品確法の規定
すでに、売買契約の場合で述べたように、請負契約の場合も、新築住宅の場合は、この存続期間について特別の規定があります。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、新築住宅の請負契約の場合にも、「建物の引き渡しを受けた時から10年間」は瑕疵担保責任を追及できるとしています。上記のように、2年の経過によってあらゆる瑕疵について瑕疵担保責任を追及できなくするというのは注文者にあまりに不利益だからです。
まずここでいう「新築」というのは、建築してから1年以内の建物でまだ人が住んだことがない建物をいいます。ですから、完成から1年を超えた建物、1年以内であってもすでに人が住んだ建物は「新築」ではなくなり、「中古」となりますから、この法律の適用はありません。
次に、この法律で可能な瑕疵担保責任の追及の方法は、瑕疵の修補請求、これに代わる又は修補請求とともにする損害賠償請求ですから、売買契約の場合(売買の場合は損害賠償請求のみ)と異なり、追及の方法は旧民法の場合と同じです。
ただし、品確法により、これらの請求ができるのはすべての瑕疵ではなく、「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」に制限されています。「構造耐力上主要な部分」というのは、基礎、土台、柱、壁、梁などの建物にかかる荷重や、地震力などによる震動や衝撃を支える部分をいいます。「雨水の浸入を防止する部分」というのは文字どおり、雨などが建物内に浸入するのを防止する屋根や外壁など、これらに設けられた開口部のサッシや戸などの建具など、さらには建物内に造られた雨水の排水管をいいます。これらの部分に瑕疵があれば、10年間の瑕疵担保責任を追及できます。
そして、この品確法の規定は「強行規定」といわれるもので、注文者と請負人間でこの期間を短縮したり、上記の瑕疵の内容を制限したりする契約や同意は無効になります。
(2)新民法の適用がある場合(つまり2020年4月1日までに請負契約を締結した建物の場合)
新民法では、請負契約についても、これまで述べてきました旧民法の規定を次のように改正しました。
① 新民法では、旧民法の請負の瑕疵担保責任に関する規定はすべて削除され、請負契約における瑕疵担保責任に関する規律は、新民法559条(有償契約への準用規定)により、売買契約の担保規定(新民法562条から564条)を準用するという形になりました。つまりすでに売買契約の場合に述べました、「追完請求」(新民法562条)、「報酬減額請求」(同563条)、
「損害賠償請求」(同564条)の規定がそのまま請負契約にも準用されることになりました。
② したがって、まず、請負契約の場合も、「瑕疵」という言葉を使わず、「目的物(ここでは建物)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物」という表現に変わっています。これは「契約不適合」と呼ばれます(新民法562条などの559条による請負契約への準用)。
ただ、この「契約不適合」の内容は、旧民法の「瑕疵」の内容と同様に考えて良いと思います。つまり「契約不適合」というのは、仕事の目的物に、❶請負契約に定めた内容と異なる品質等がある場合❷法令に違反する品質等がある場合❸通常の設計・施工水準に達していない場合に該当すると考えて良いでしょう。
③ このような「契約不適合」があった場合、注文者は、請負人に対し、目的物(ここでは建物)の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しを請求することができるとしました(新民法562条)。これを「注文者の追完請求権」と呼んでいます。
④ ただ、このような注文者による追完請求に対し、請負人は「注文者に不相当な負担を課すものでないときは、注文者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」としています(同条但書)。
⑤ 注文者が相当の期間を定めて上記の追完を求めても、請負人がその期間内に追完をしないときは、注文者は、その不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができるとしました(新民法563条1項)。ただし、請負人が追完を拒絶する意思を明確に表示したときなど一定の場合には、追完請求を先行しなくても直ちに代金減額請求できるとしました(同条2項)。
このように代金減額請求を行うには、まず追完請求(例えば修補請求)を行うことを原則とすることについては批判もあります。そのため直ちに代金減額請求を行うことができる場合をできるだけ広く認めていくべきす。
⑥ さらに、上記の追完請求や代金減額請求をする場合、あるいはそのような請求をしなくても、新民法415条の規定(債務不履行を理由とする)損害賠償請求や契約の解除(新民法541条、542条)もできるとしています。
ただし、旧民法の場合の瑕疵担保責任は無過失責任とされていましたので、修補請求に代えてする損害賠償請求の場合も請負人の過失は問題とされていませんでした。ところが新民法では過失を前提とする損害賠償請求一般と同じ取り扱いをするということになると、請負人の過失の存否が一応問題となることになります。しかし請負契約の場合は、売買契約の場合と異なり、自ら施工して契約不適合を生じさせたのですから、そこには少なくとも過失の存在は認められることになるでしょう。
⑦ 上記のような契約不適合の場合の注文者の追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権および契約の解除は、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならず、これをしないと追及できなくなるとしています(新民法637条1項)。ただし、請負人が引き渡しの時にその不適合を知っていたか、又は重大な過失により知らなかったときは、この期間制限は適用されないとしています(同条2項)。つまり、通常の権利と同じように「権利を行使することができることを知った時から5年間」、又は「権利を行使することができる時から10年間」で時効によって消滅することになります(新民法166条1項1号及び2号)。
ただ、この新民法637条1項の規定については、請負契約においてその契約書に旧民法の時と同じように、例えば「追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除は、建物の引き渡しの時から2年が経過したときはすることができない」という条項を請負人が入れ、そのため旧民法の時と同じ不当な結果をもたらすことになる危険性があります。
しかし、仮にこのような条項が契約書に入れられていても、少なくとも上記新民法637条1項のように「請負人が引き渡しの時にその不適合を知っていたか、又は重大な過失により知らなかったときは、この期間制限は適用されないと」し、まったく期間制限がない状態、つまり、通常の権利と同じように「権利を行使することができることを知った時から5年間」、又は「権利を行使することができる時から10年間」で時効によって消滅する(新民法166条1項1号及び2号)と解すべきです。
⑧ 品確法との関係
新民法の上記のような改正に伴い、品確法の規定も、従来の修補請求権と損害賠償請求権だけでなく、追完請求権(修補請求もそのひとつ)、代金減額請求、損害賠償請求、解除権の行使を認める内容に改正されました(改正品確法95条)。
なお、品確法が適用される場面、すなわち新築であること、瑕疵(契約不適合)が「構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分」に制限されていること、強行規定であることに変更はありません。
さらに、品確法に基づくこれらの請求権は、品確法の特別法的性格から、通常の権利と同じように「権利を行使することができることを知った時から5年間」で消滅時効にかかる(新民法166条1項1号)と解するのはあやまりで、単に「権利を行使することができる時から10年間」で時効によって消滅する(新民法166条1項2号)と解すべきです。
3 まとめ
以上、建物の売買や請負契約の場合に、瑕疵(契約不適合)があったときの責任追及の法的手段について、旧民法と新民法に分けて簡単に述べました。
でも、これらの規定は、なかなか理解するのが困難ですので、分からないときや疑問があれば早めに法律専門家に相談されるのがいいでしょう。
とくに私が申し上げておきたいのは、上記のように民法等は責任追及ができる期間を制限していますので、早めの対応が必要不可欠だということです。欠陥があるのかないのか、その欠陥はどのようなものなのかをできるだけ早く建築専門家(欠陥検査を行う建築専門家)に相談されて検査をされることが必要ですし、欠陥が見つかれば、売主、施工業者、設計者に欠陥の補修や損害賠償を文書で求めることが必要です。
なお、今回は触れませんでしたが、上記の責任追及のほかに、民法の不法行為責任に基づく損害賠償請求を行うこともできます。この点についてはまたの機会に改めて述べたいと思います。
以上